戦国時代の幕開け!下剋上って何?
歴史の授業で必ず出てくる「戦国時代」。聞いたことはあるけれど、どんな時代だったのか、いまいちピンとこない人もいるかもしれませんね。戦国時代を一言で表すなら、「下剋上(げこくじょう)」がキーワードになります。
「下剋上」とは、身分の低い者が高い身分の者を倒し、のし上がっていくことを指します。
例えば、家来が主君を裏切ってその地位を奪ったり、農民が力をつけて武士を倒したり…といったことが実際に起こったのが、戦国時代なんです。

それまでの日本の社会では、身分制度がしっかりしていて、なかなか身分の低い者がのし上がることはありませんでした。
しかし、戦国時代は、実力さえあれば誰でも天下を狙える、まさに弱肉強食の時代だったのです。
戦国大名ってどんな人?
戦国時代を語る上で欠かせないのが、「戦国大名」の存在です。
戦国大名とは、戦国時代に各地で力を持ち、自分の領地を支配した武将たちのこと。彼らは、「下剋上」の風潮の中で、戦乱を勝ち抜き、自分の領地を広げていきました。

戦国大名たちは、自分の領地を「国」のように扱い、政治や経済を自分たちの手で行っていました。つまり、戦国大名たちは、それぞれの領地で「王様」のような存在だったのです。
群雄割拠ってどういう意味?
「群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)」という言葉を聞いたことはありますか?
「群雄」とは、たくさんの戦国大名たちのこと。「割拠」とは、領地を分割してそれぞれが支配することを意味します。
つまり、「群雄割拠」とは、戦国大名たちが日本をいくつにも分割して、それぞれが独立した国のように支配していた状況を表しているのです。

現代の私たちには少し想像しにくいかもしれませんが、大和朝廷が成立する前の日本のように、戦国時代も各地にたくさんの「国」が存在していた、と考えれば分かりやすいかもしれません。
戦国大名は独裁者?
戦国大名たちは、自分の領地では誰にも邪魔されず、自分の思う通りに政治を行うことができました。彼らは、法律を作ったり、税金を集めたり、家来に命令したりと、まさに「独裁者」のような存在だったのです。

戦国大名たちは、自分の領地では神様のような存在であり、絶対的な権力を持っていたと言えるでしょう。
まとめ
- 戦国時代は「下剋上」の時代!
- 戦国大名は自分の領地で「王様」!
- 「群雄割拠」で日本はたくさんの国に分かれていた!
- 戦国大名は自分の領地では「独裁者」!
タグ
#戦国時代,#下剋上,#実力主義,#群雄割拠,#戦国大名,#日本の歴史,#日本史,
これらの情報を参考にしました。
[1] ダイヤモンド・オンライン – 戦国時代を呼んだ「山名宗全・細川政元」、実力主義へ社会を … (https://diamond.jp/articles/-/316644)
[2] 東洋経済オンライン – 「最強の戦国武将」は結局、誰だったのか? 「武勇、知略 (https://toyokeizai.net/articles/-/173620?display=b)
[3] スタディアップ – 中学受験 歴史 戦国時代の重点ポイントまとめ (https://www.studyup.jp/contents/shakai/rekishi-sengoku.html)
[4] 貸切温泉どっとこむ – 【第2回】旧勢力の内紛と新勢力の台頭/関東三英傑の誕生 … (https://www.kashikiri-onsen.com/kantou/gunma/sarugakyou/sengokushi/commentary02.html)


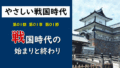
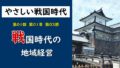
コメント